3.検証データ
本実用プログラムは、魚礁に限らず海中構造物であれば汎く適用できますが、前述のとおり、当面は、今日まで感覚的にしか理解できていなかった「魚礁を設置することによる流れの変化」についての多角的な検証を行っていきたいと考えています。様々なパターンの「魚礁の配置」、「積重ね」、「単体構造等」を設定し、どの様な流れが形成されるのかの基礎データを少しづつ蓄積しているところです。検証データの一例をPDFファイルとして添付しますので参照下さい。例えば、漁業者からよく「沈船が一番良く魚が付く」と聞きますが、サムネール番号の「シート20」を見るとそのことが少し理解できます・・・。
※具体的なデータは別添の「PDFファイル」を参照下さい! (配布は終了しました。)
4.おわりに
漁場分野においては、事業の高度化・多様化に伴い、より高度な解析能力が求められるようになっています。その典型がシミュレーションに代表される数値解析業務です。このプログラミングを通じて感じたことは、近年におけるコンピューターの処理能力が格段に向上したことにより、今までワークステーションクラスの電算システムを備えた一部の研究施設・研究者しか実現できなかったことが、汎用パソコンでもかなりのレベルまで実現可能であると実感したことです。本プログラムを例にとると、加算乗除の演算回数は数十億回にも及びますが、これをわずか数分で処理します。もし関数電卓を使用して、これを実行しようすれば数カ月は要するでしょう。このことは「小規模事業所であってもシミュレーション業務が可能な時代に入ってきた」ことを意味します。前出のとおり、本プログラムではパソコンの処理能力及びExcelの行数制限により、格子数を54,000に固定していますが、この点についてもプログラミングの工夫と、より処理能力の高いパソコン導入により、さらに拡張できる問題です。また、その他の技術的な問題点として、物質の移動経路は流向・流速をどれだけ詳細にみても、ほとんど判読できないという盲点があります。海域の基礎生産に関わる栄養塩類やプランクトンの移動分布を再現するためには、もう一歩の工夫が必要となります。この点に関しては、現在注目されつつある内部波や流線の解析というアプローチ方法もありますが、物質が微細であることと、それらが受動的な動き(浮遊物質の動き)であることから、実際の動きは物質の濃度変化として「拡散方程式」で再現できるのではないかと考えています。この考え方の具体化は、「拡散シミュレーション」との連係で解決できます。つまり、両プログラムを同一格子数で設計し、まず構造物の座標と初期流速を与え、流動再現シミュレーションにより流向・流速を算出する。次に、その結果を濁り拡散シミュレーションの計算条件として読み込み、続いて栄養塩類や植物プランクトンの初期濃度(あるいは細胞数)を与え、その分布を経時的に計算・図示する。このことにより、さらに一歩進んだ解析手法が開発できると考えられます。
なお、開発を行っている当方は流体力学の研究者でもなれれば専門家でもありません。率直に言って、流体力学分野の学問的な奥の深さはたいへんやっかいであり、科学的な裏付けを追求すれば誰もが自ずと迷路に陥ることでしょう。しかし、存在しないなら自分で何とか作るしかありません。完成度は低くても何らかの「たたき台」がなければ何事も始まりません。シミュレーションはあくまで机上の計算結果であり、各種パラメーターの簡略性からみて絶対的な予測は到底不可能であることを肝に銘じ、試行錯誤の中から現場に精通した漁業者の感覚に近い結果(相対的結果)を導き出し、その際のパラメーター設定値を経験値として次の計算に役立てることが重要ではないかと考えています。流体力学の専門家の方々に、もっとこの分野に目を向けてもらい、誰もが利用できる実用プログラムを公開してもらいたいものです。


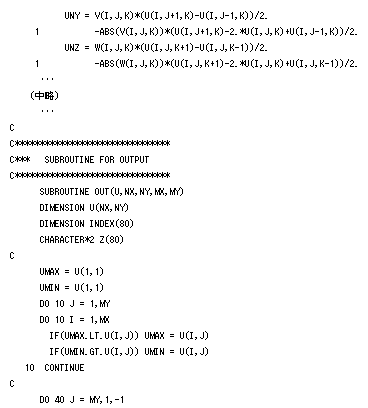
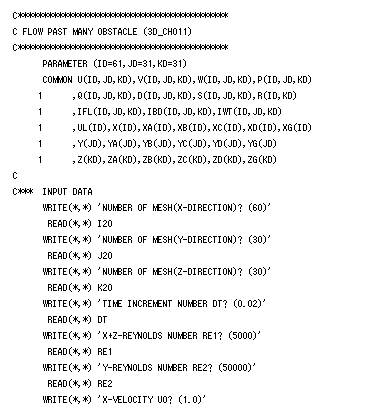
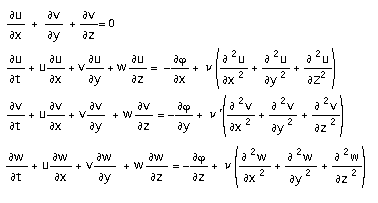
2.実用プログラムの解説と特徴
基本的な話になりますが、海水の流れは、一般に非圧縮性ナビエ・ストークス方程式に支配されます。本シミュレーションでは、事前に設定した区域内に、左側から一様流(任意設定の流速ベクトル成分)が侵入してくる条件下の3次元モデルを想定し、下記に示す偏微分方程式(基本式)を差分法で解く方法を採用しています。計算に用いた実用プログラムは、河村(「流れのシミュレーションの基礎」インデックス出版、2002年)が示したフラクショナルステップ法による解法プログラムコード(Fortran言語)を参考に、加筆・修正し、それをアプリケーションファイルとしてコンパイルしました。アプリケーション化されたファイルの実行の際には、いくつかの計算条件を対話形式で入力できるようにし、これにより計算結果をテキストファイルとして書き出し、計算結果の出力(図化)には、汎用性を考慮し、MS_Excel(マクロ機能の利用)を用いることとしました。つまり、複雑な計算部分はFortran言語で、図化はMS_Excelという方法を用いています。
(ポテンシャル流の基礎方程式)
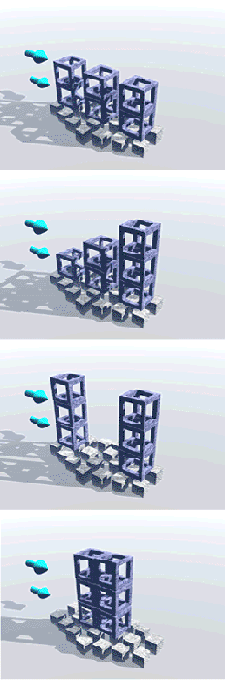
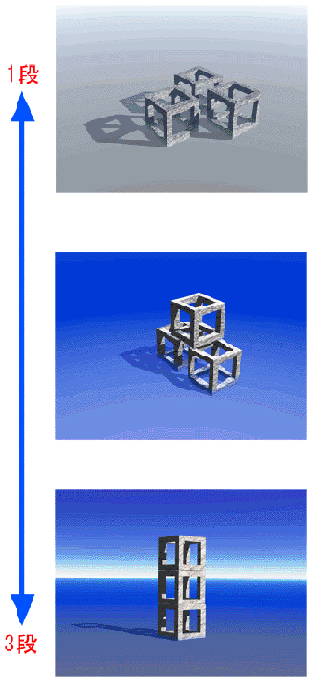
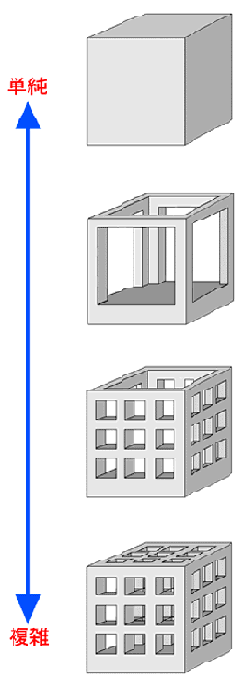
ここで、
u :速度のX成分 ν,ν':μ/ρ(渦動粘性係数)
v :速度のY成分 p :圧力
w :速度のZ成分 μ:粘性率
ψ:p/ρ ρ:密度
なお、実際の計算段階においては、計算範囲、格子数(XYZ方向)、初期流速、計算ステップ数、レイノルズ数、境界条件等の設定が必要となります。設定値は項目によっては計算結果に大きな影響を及ぼすこととなり、特にレイノルズ数(Re=UV/ν)については、渦流形成や影響範囲を大きく左右する係数なので、水平方向(X方向)、鉛直方向(Y方向)、奥行き方向(Z方向)それぞれについて調整を加えられるよう設計しています。特徴としては、計算結果の図化(可視化)はMS-Excelのグラフ作成機能を用いるので、任意の構造物を配置した条件下の計算結果をいったん書き出しておけば、どのパソコンでも、任意の断面のベクトル図、等流速値線、湧昇効果等を再現することができます。また、最大の利点は、様々な考え方や計算ケース、現場条件を想定し、変数や計算式を自由に変更できる点にあります。
以上、長所だけを強調してきましたが、改良すべき点もいくつかあります。本プログラムでは通常格子の3次元メッシュを設定し、計算だけであればコンピューターのメモリーが許す範囲内において、ほぼ無制限の格子数が設定可能ですが、その後の図化ではMS-Excelのセル行数(65,000行)の制限を受け、195,000個(X,Y,Z方向の流速データ数は65,000行×3方向=195,000個)以上のデータの扱いは大変困難です。そのため現モデルでは60格子(X方向)×30格子(Y方向)×30格子(Z方向)=54,000格子に固定しています。但し、1格子のスケールは自由に変更できるので、1格子を1mに設定すれば60m×30m×30mの空間、5mに設定すれば300m×150m×150mの空間を対象範囲とすることができます。この格子数については、増やした分だけ細かな構造物を配置できることになりますから、もう少し格子数を増やしたいのですが、現行パソコンの処理能力及びハンドリングを考慮すれば、この程度の格子数が妥当(限界)のようです。
(Fortranプログラムコードの一部)
●魚礁の流体力学;流動再現シミュレーション「漁場開発部:桑本」
1.はじめに
長崎支所が実施している魚礁分野の業務において、最も重要な技術的課題の一つに、最適な配置、積重ね、単体構造等を定量的に比較検討するための解析手法の開発があります。最適な配置等を決定するには、本来、海域環境条件、対象魚種、操業形態等を含めた総合的な解析が必要ではありますが、魚礁を設置することによりもたらされる環境変化の第一義的な要因が「流れ」であることは論じるまでもなく、蝟集効果(魚群形成)、底質変化、湧昇効果等に関しては「流れの変化」を定量的に把握することで、一定の論理的説明が可能となります。つまり「流れの変化」を検討することは、事前・事後を含めて、魚礁事業における最も基本的かつ重要なことなのです。しかしながら、こうした予測・検証は、技術的・経費的制約もあってか、今日までほとんど行われてきませんでした。これは、科学的側面からみた魚礁事業の重大な論理的欠落部分と認識しています。現状においてもし仮に、この様な「流れの変化」の予測を行う場合、1)大学機関等に依頼してシミュレーションを実施するか、2)水槽実験を実施するか、この2つの方法しかなく、実施困難であるという現実的問題点を抱えていたことも事実です。一方で、魚礁メーカー等の資料(パンフ・技術資料)には、渦流効果、湧昇効果等の言葉は乱舞していますが、それを定量的に示したものはきわめて少ないのが現状です。配置計画を決定する段階においても同様に、魚礁の高さ、積重ね、設置間隔はあくまで定性的な検討にとどまり、定量的な資料は安定性・数量計算に関するものに限られています。こうした現状を踏まえ開発したのが「流動再現シミュレーション」の実用プログラムです。端的に表現すれば、水槽実験で使用される模型水路をコンピューター上で想定し、構造物配置後の流向・流速を計算し、断面図として図化するソフトウェアー群です。具体的には、図-1に示すとおり、魚礁内部の複雑性や配置パターンを変化させることで、流れがどう変化するのか比較検討しています。